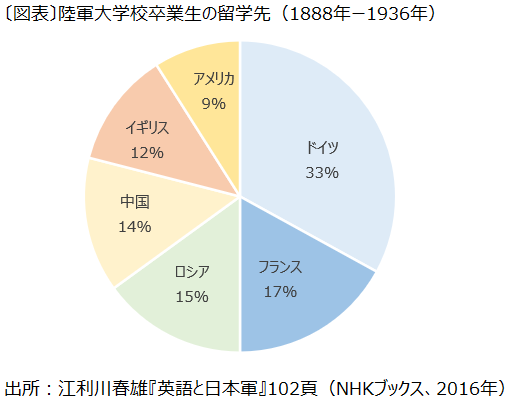著名なコンサルティング会社のマッキンゼー社による、企業経営者のダイバーシティが企業業績に与える影響について調査した論文がある。Vivian Hunt et al., Delivering through Diversity, (2017) によると、企業の役員の性別や民族に多様性があるほうが好業績であることを論じている。
そこで、この論文の中で使用されている図表を見てもらいたい。2014年に性別の多様性がある企業の上位25%は、下位25%の企業よりも15%業績が良いことを示している。あるいは、2014年に民族の多様性がある企業の上位25%は、下位25%の企業よりも35%業績が良いことを示している。2017年のグラフも同じである。筆者は論文の趣旨は理解できたが、どうしても理解できない数字があった。それは、棒グラフ内にある2014年の性別多様性の47、54、民族多様性の43、58及び2017年の性別多様性の45、55、民族多様性の44、59である。
〔図表〕

結局わからないのでネイティブの知人に確認してみた。しかし、この数字は企業数だという回答であった。ただ、どうしても論理的に説明がつかない。電卓を叩いて確認するものの納得できなかった。また、注釈1)に”Average EBIT margin”とあるが、MBAで学んだことがない私でも、47%や54%ではあまりにも大きいEBIT margin(EBIT=税引前当期純利益+支払利息-受取利息)になってしまうことはわかる。せいぜい良くて10%とか15%ではないか。よって、EBIT marginでもない。そこで、英語がほぼネイティブのヨーロッパ人にも聞いてみたが、1週間経っても回答がなかった。
ところが、意外な人が回答をくれた。妻である。妻の母語はフランス語で英語は第二外国語、日本語は第三外国語である。ただ、大学時代に経済学を専攻した時期があり、これは中央値を50として、上位25%の企業が54で下位25%の企業が47だと説明してくれた。This makes more sense!!(これは合点がいく!!)である。
ここで得られる示唆は英語の能力も大切であるが、当該分野の背景を知らないと理解できないことがあるということかもしれない。バックグラウンドがあるとないとでは、同じ英文レポートを読んでも理解力に差がでるということである。たしかに、表題にmedian(中央値)という単語が使われているので、それに気づけば中央値を50としていることがわかったかもしれない。それに気づかない自分も情けないが、やはり経営学や経済学の訓練をうけていないので、当該論文の理解も浅いのだと感じた。日本語で徹底的にこの分野の訓練を受けていれば英語力が弱くても理解できることはあるのかもしれない。
英語で専門分野を学ぶことの重要性は繰り返し述べているが、圧倒的な日本語力があるのであれば、まずその分野の知識を徹底的に積み上げることを優先してもよいともいえる。そうしておけば、当該分野における英文のレポートや論文も容易に理解できることになる。英語、英語と英語漬けもいいが、専門知識を磨き上げることも忘れてはならない、という教訓かもしれない。ネイティブがわからない英語論文をノンネイティブが理解できるということもあるわけなので。
もう一つ感じることは、マッキンゼー社には圧倒的な天才や秀才が多いのであろうが、普通の人々に理解してもらうための技術が不足しているのではないかと思った。頭の良い人は自分の中で論理が完結し、その難しい論理をやさしく人に伝えることが苦手なのかもしれない。難しいことをやさしく伝えるという技術は、ぜひとも磨きたいものである。そのせいもあってか、2020年のVivian Hunt et al., Diversity wins, (2020) では、”Likelihood financial performance vs. the national industry median”という注釈表記がなされており、よりわかりやすくなっていた。しかも、グラウの中央値である50の点線が引かれている。読者からクレームがあったのかもしれないが、分かりやすさが改善されているのがわかるので機会があれば確認してみてほしい。